長年にわたって安全運転を続けてきたドライバーの証である「ゴールド免許」。もしゴールド免許を持っている状態で違反をしてしまったら、どのような影響があるのでしょうか。また、物損事故の場合はどうなるのか、再びゴールド免許を取得するまでにはどのくらいの期間が必要なのかなど、気になる点は多いでしょう。
目次
ゴールド免許の取得条件
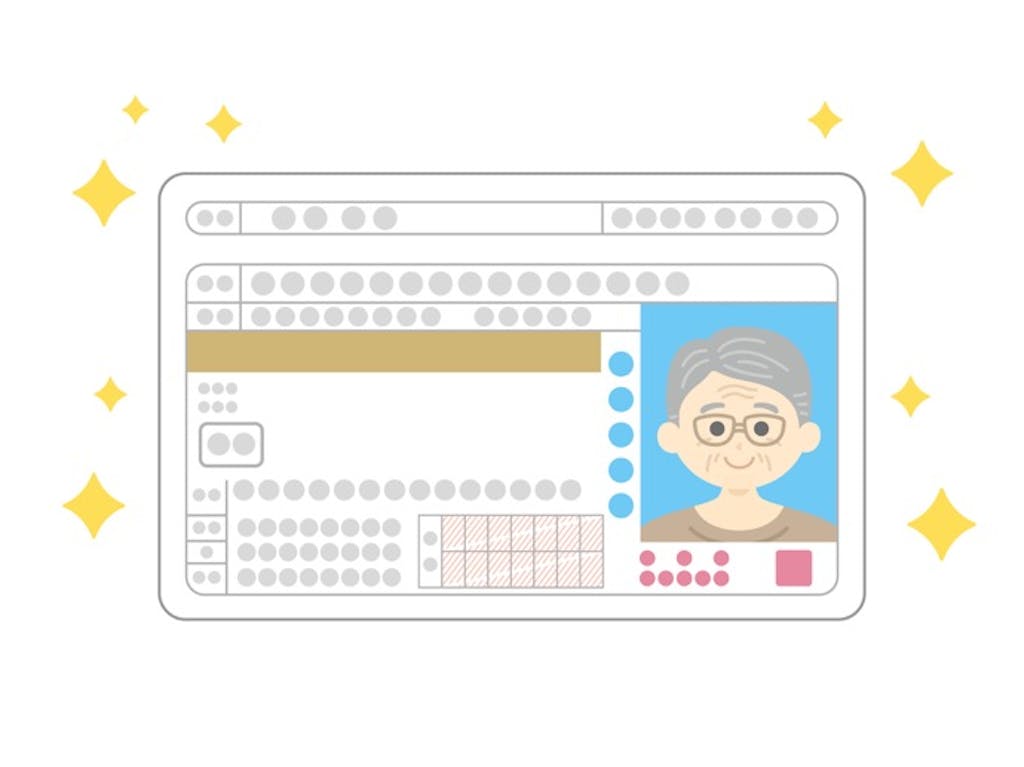
この記事では、ゴールド免許の基本的な取得条件から、違反した場合の影響、再取得の流れまで、詳しく解説していきます。
まず、ゴールド免許がどのような条件で取得できるのかを確認しておきましょう。有効期限部分に金色の帯が付いたゴールド免許は、優良運転者の証として交付されるものであり、取得には以下の3つの条件が設けられています。
- 免許の継続期間が5年以上であること
まず、運転免許証を取得してから継続して5年以上保有していることが必要です。新規取得者の場合、最初の免許は有効期間が3年間、初回更新も3年間となるため、最短でも6年程度の期間が必要となります。 - 基準日前5年間、無事故・無違反であること
基準日とは、免許更新年の誕生日の40日前のことです。つまり更新年の誕生日の41日前からさかのぼって5年間、事故や違反がないことが条件となります。 - 重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしていないこと
他人に重大な交通違反をするように仕向けたり、公道以外の場所(駐車場や私有地など)での人身事故を起こしたりした場合は、道路交通法上は無違反であっても、ゴールド免許の取得はできません。
ゴールド免許に影響しない違反もある
条件の1つに無事故・無違反とありましたが、実はすべての交通違反がゴールド免許に影響するわけではありません。違反点数が加算されない軽微な違反については、ゴールド免許の取得や維持に影響しないのです。
具体的には、以下の5つの違反が該当します。
- 免許証不携帯:運転時に免許証を携帯していない場合
- 泥はね運転:水たまりなどで他人に泥水をかけてしまう行為
- 警音器使用制限違反:不必要な場所でクラクションを鳴らす行為
- 公安委員会遵守事項違反:各都道府県が定める運転ルールの違反
- 運行記録計不備:特定の事業用車両などに必要な装置の不備
これらの違反は、反則金の支払いは必要ですが、違反点数が加算されないため、ゴールド免許への影響はありません。
物損事故を起こした場合
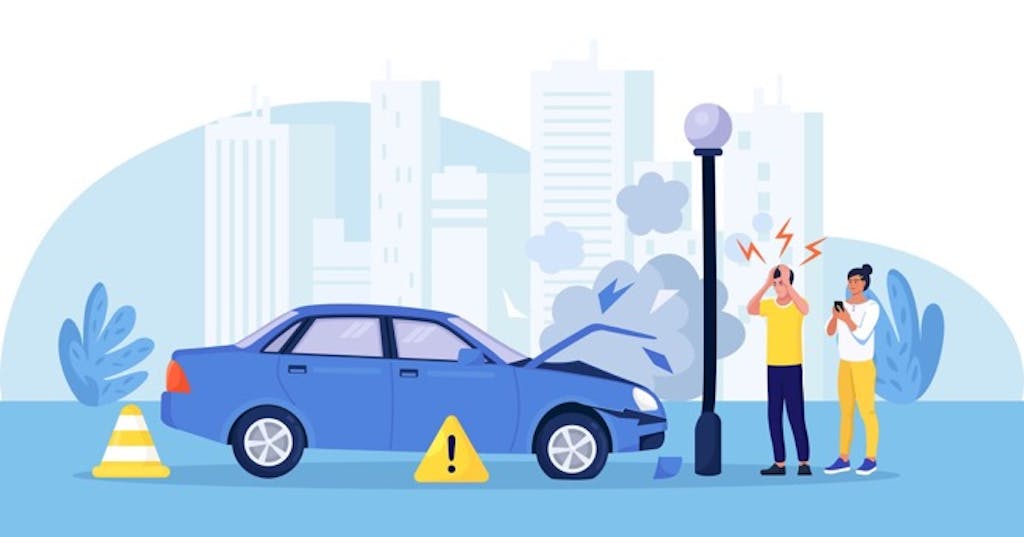
なお、ゴールド免許の判定において「事故」とは人身事故のみを指しており、物損事故については影響しません。物損事故とは、人にケガがなく、車両や建物などの物に損害が発生した事故のことです。
例えば、他の車両と接触してしまった場合や、ガードレールや電柱に誤って衝突してしまった場合でも、人的被害がなければ物損事故として扱われ、ゴールド免許の維持に影響はありません。
物損事故における例外
ただし、物損事故であってもゴールド免許に影響する事例もあります。ここでは3つの代表的なケースを確認しておきましょう。
- 当て逃げの場合
物損事故を起こした後、道路上での危険防止や警察への報告など必要な措置を取らずに現場から立ち去った場合は「当て逃げ」となります。この場合、安全運転義務違反(2点)と危険防止措置義務違反(5点)で合計7点の違反点数が加算されて「一発免停」となり、ゴールド免許は失われます。加えて懲役や罰金などの刑事罰が科せられることもあります。
- 交通違反が原因の場合
物損事故であっても、飲酒運転や速度超過などの交通違反が原因で起こした場合は、その内容に応じて点数が加算されます。こちらもゴールド免許を引き継げなくなるほか、違反の内容や累積点数、前歴の有無などによって免許停止や免許取り消しなどの厳しい処分を受けることになります。
- 建造物を損壊した場合
そのほかにも、他人の建物や公共施設などを損壊した場合は、物損事故であっても行政処分や刑事処分が科せられ、ゴールド免許に影響する場合があります。
3カ月特例とゴールド免許は無関係
交通違反の点数計算には、いわゆる「3カ月特例」という制度があります。これは、過去2年間無事故・無違反のドライバーが3点以下の軽微な違反をした場合、その後3カ月間無事故・無違反を続けることで、違反点数の累計計算から除外されるという制度です。
しかし、この3カ月特例は違反点数の3年間の累計計算にのみ適用される制度であり、ゴールド免許の判定には一切関係ありません。たとえ3カ月特例が適用されたとしても、違反の事実があることに変わりはないため、次回の更新時にはゴールド免許からブルー免許に変更されます。
ゴールド免許からブルー免許になるデメリット
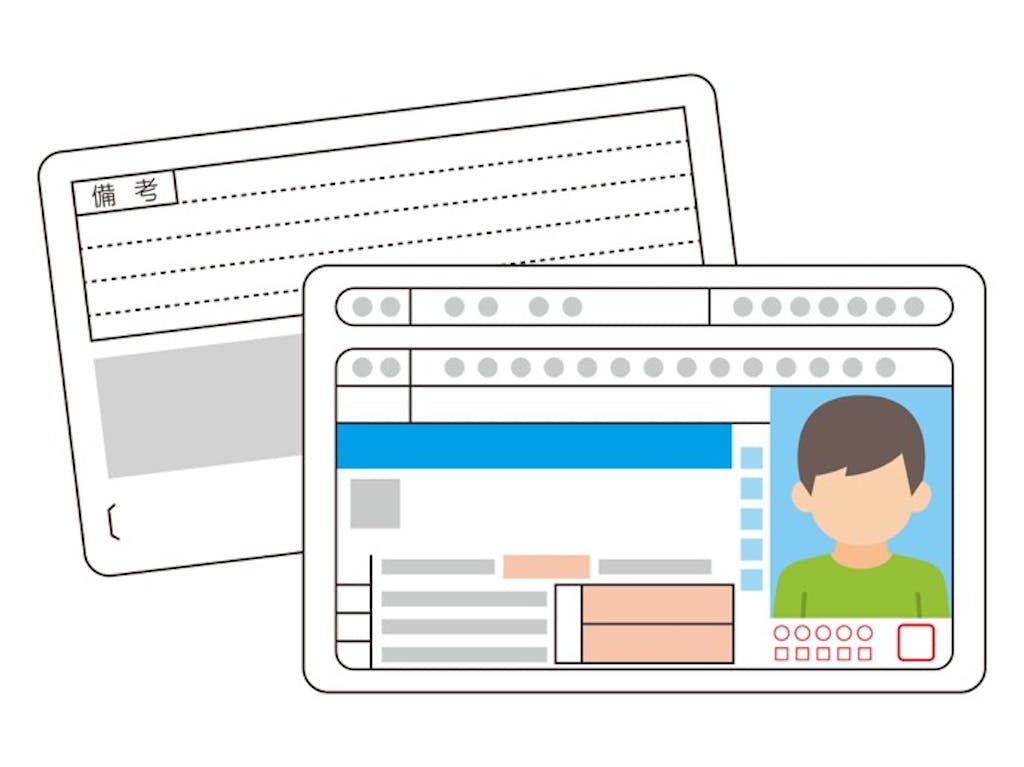
ゴールド免許からブルー免許になることで、これまで受けていた優良運転者としての特典が失われます。どのようなデメリットがあるのか見てみましょう。
免許の有効期限が短くなる場合がある
ゴールド免許の有効期間は原則として5年間ですが、ブルー免許になると有効期間が短くなる場合があります。
- 一般運転者(ブルー免許):5年間
- 違反運転者(ブルー免許):3年間
違反の内容や回数によって違反運転者に分類された場合、免許の有効期間が3年間となり、更新頻度が高くなります。具体的には過去5年間に軽微な違反が1回以下の場合は一般運転者、4点以上の違反や複数回の違反、人身事故を起こした場合などは違反運転者となります。
免許更新における優遇が受けられなくなる
また、ブルー免許になると以下の更新時の優遇が受けられなくなります。
講習時間の違い
- 優良運転者講習(ゴールド免許):30分
- 一般運転者講習(ブルー免許):1時間
- 違反運転者講習(ブルー免許):2時間
講習手数料の違い
- 優良運転者講習(ゴールド免許):500円
- 一般運転者講習(ブルー免許):800円
- 違反運転者講習(ブルー免許):1,350円
更新場所の制限
ゴールド免許保有者は最寄りの警察署での免許更新手続きが可能ですが、違反運転者の場合は運転免許試験場や免許センターなど限られた場所でしか更新できません。これにより、交通費や時間の負担が増える場合もあるでしょう。
自動車保険に割引が適用されなくなる
多くの保険会社では、ゴールド免許保有者に対して「ゴールド免許割引」を提供しています。これは、長期間にわたって無事故・無違反を続けている運転者は事故を起こすリスクが低いと判断されるためです。
ブルー免許になると、この割引が適用されなくなり、保険料が上がる可能性があります。割引率は保険会社によって異なりますが、年間数千円から1万円以上の差が生じる場合もあります。
ただし、契約期間中にゴールド免許からブルー免許に変わっても、その期間中の保険料は変わりません。影響が出るのは次回の契約更新時からとなります。
ゴールド免許の再取得までには何年かかる?

それでは一度ゴールド免許からブルー免許になってしまった場合、再びゴールド免許を取得するまでにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。
一般運転者になった場合
軽微な違反により一般運転者(ブルー免許)になった場合、違反した日から5年間無事故・無違反を続けることで、次回の更新時にゴールド免許を取得できます。一般運転者の免許有効期間は5年間なので、最短5年間でゴールド免許の再取得が可能ですが、更新のタイミングによっては10年かかることもあります。
違反運転者になった場合
ゴールド免許から違反運転者になった場合も同様に、5年間の無事故・無違反がゴールド復活の条件となります。具体的には以下の2パターンに分かれます。
違反後の無事故・無違反期間が2年以上ある場合
違反をした日から次の更新までの期間が2年以上あり、その間無事故・無違反を続けた場合は、2回目の更新でゴールド免許に復活でき、実質的にブルー免許の期間を3年間で済ませられます。これは、違反した日から5年間の無事故・無違反期間のうち、ゴールド免許のまま過ごした2年以上の期間もカウントされるためです。
違反後の無事故・無違反期間が2年未満の場合
違反した日から次の更新までの期間が2年未満の場合は、5年間の無事故・無違反条件を満たすことができないため、2回ブルー免許で更新することになります。その後も無事故・無違反を続けていれば、3回目の更新時にはゴールド免許を取得できます。この場合、ゴールド免許の再取得までに6~8年程度の期間が必要となります。
まとめ
ゴールド免許は5年間の無事故・無違反が条件となる優良運転者の証です。違反や事故を起こしてしまうと次回の更新時にはブルー免許になり、講習時間の延長や手数料の増加、自動車保険割引の適用除外などさまざまなデメリットが生じます。ただし、物損事故や違反点数の付かない違反については基本的にゴールド免許に影響しません。万が一ゴールド免許の資格を失ってしまった場合でも、最短3年程度でゴールド免許の再取得が可能です。
ゴールド免許は一朝一夕で取得できるものではありませんが、日々の安全運転の積み重ねによって必ず手に入れられる資格です。自分や周囲の人々を守るためにも、常に余裕を持った運転を心がけることがゴールド免許取得・維持への近道となります。




